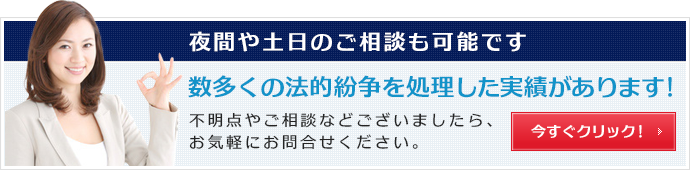本件の原告は、自動車用タイヤの製造販売を主たる業務とし、地図やレストランガイドの提供でも有名なフランス企業であるミシュラン社です。
本件の被告らは、「株式会社ミシュラン」の商号を被告会社の営業を示す表示として使用し、サンドイッチ、弁当等の製造販売等を行っていたため、原告が「株式会社ミシュラン」の商号の使用の差止請求等を求めて起こしたのが本件訴訟です。
主な争点は、①原告の営業表示及びその周知性、著名性、②混同のおそれの2点です。
東京地裁は、原告の周知性、誤認混同のおそれがあることを認め、商号の使用差止、商号の抹消登記手続、損害賠償の請求について認めました。
東京地裁の判断は以下の通りです。
争点①原告の営業表示及びその周知性、著名性について
「原告は、一八六三年に設立されたフランスの会社である。...原告は、昭和四〇年代以降、アメリカ合衆国の市場への本格的進出、高性能タイヤの開発などにより、タイヤの販売量を伸ばし、昭和五三年ころには、ラジアルタイヤでは世界最大規模となり、現在、タイヤメーカーであるグッドイヤー、プリヂストンと、世界のタイヤの市場占有率を競っており、最近の数年間は、世界第一位であった。...原告は、明治三三年(一九〇〇年)から、地図及びレストランガイドの提供を始めた。原告のレストランガイドは、『ミシュラン』という名称で知られており、表紙が赤色であることから、『ミシュラン』の『レッドガイド』と呼ばれ、毎年三月に一八〇万部出版されるが、六月ころにはほとんど売り切れてしまう状態である。...我が国においては、昭和五二年、洋書店の丸善から、原告のレッドガイド及びグリーンガイドの英語版、フランス語版、ドイツ語版等並びにフランス、ヨーロッパなどの地図について、宣伝パンフレットが発行された。...経済誌である『日経ビジネス』の平成八年七月二二日号には、アメリカ合衆国の経済誌『フィナンシャル・ワールド』が同月に発表したデータをもとにした代表的なブランドの資産価値が掲載されており、原告のブランドである『ミシュラン』の資産価値は、五三億四五〇〇万ドルで世界第二三位であり、ハイテク分野の『マイクロソフト』、食品分野の『ナビスコ』などのブランドと同程度の価値があることが記載されている。右認定の事実によれば、『ミシュラン』の表示は、我が国において、遅くとも昭和五二年ころには、原告の商品及び営業を示す表示として広く認識されており、それ以後、現在に至るまで、広く認識されているものと認められる。」
争点②混同のおそれについて
「企業の経営が多角化した今日においては、当該企業自体はもとより、当該企業と親会社、子会社の関係にある企業や系列企業が、当該企業が本業としていた分野以外の事業に携わることが少なくないため、周知表示の主体と類似表示の使用者との間に直接の競業関係が存在せず、周知表示の主体の本業と異なる分野の事業に類似表示が用いられた場合にも、類似表示の使用者と周知表示の主体との間に営業上の密接な関係があると誤信される可能性が高く、このような誤解が生じることにより、周知表示の主体について、売上げの減少や周知表示の顧客吸引力の減殺など有形無形の損害が生じ又は生じるおそれがある。不正競争防止法は、周知表示を保護する観点から、周知表示に対するこのような侵害行為を防止しようとしているものであるから、同法二条一項一号の『混同を生じさせる行為』とは、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係ないしは同一の商品化事業を営むグループに属する関係などの密接な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である。これを本件についてみると、前記一1認定の原告の事業内容、前記一2認定の原告の営業表示の周知性、前記二認定の被告らの事業内容、前記三認定の原告の営業表示と被告会社の営業表示の類似性に照らせば、被告らが、「株式会社ミシュラン」の商号を、被告会社の営業表示として使用し、サンドイッチ、弁当等の製造販売、居酒屋の経営を行っていることは、被告らが、原告の営業表示と類似の営業表示を使用し、被告会社と原告とを同一営業主体と誤信させるか、若しくは、原告と被告会社の間に、いわゆる親会社、子会社の関係ないしは同一の商品化事業を営むグループに属する関係などの密接な営業上の関係が存するものと誤信させる行為であり、不正競争防止法二条一項一号の『混同を生じさせる行為』に該当するものと認められる。」
本件訴訟は、原告が、被告の販売するテントは、原告の商品の形態を模倣したものであると主張して、被告に対し、不競法2条1項3号、3条1項、2項に基づき、被告テントの販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、同法4条、5条2項に基づき、損害合計500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月4日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案です。 本件訴訟の争点は、被告の行為が不競法19条1項5号イ(適用除外行為)の「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」に該当するかどうかです。
原告テントの販売開始時期は平成22年10月頃であるのに対して、被告テントの販売が開始されたのは、そこから3年以上経過した平成27年5月2日なので不競法19条1項5号イにより同法3条及び4条は適用されないとの主張を被告はしました。
これに対して、原告は、平成22年10月頃から販売しているのは第1世代の原告テントであって,本件で問題としている平成25年10月15日から販売している第2世代のテントであるとの主張をしたので、不競法19条1項5号イの「日本国内において最初に販売された日」がどちらになるかが問題になりました。
結論からいうと、東京地裁は、第1世代の原告テントの販売開始日が「日本国内において最初に販売された日」に該当すると判断して、被告による被告テントの販売には、不競法19条1項5号イの適用除外事由があるとして、原告の請求を棄却しました。
東京地裁の判断は以下の通りです。
東京地裁の判断
「不競法2条1項3号及び19条1項5号イは,他人の『商品』が日本国内において「最初に販売された日』から起算して3年を経過しない間に限り,当該商品の形態を模倣した商品の譲渡行為等を不正競争行為に当たるとしたものである。その趣旨は,同法1条の事業者間の公正な競争等を確保するという目的に鑑み,開発に時間も費用もかけず,先行投資した他人の商品形態を模倣した商品を製造・販売し,投資に伴う危険負担を回避して市場に参入しようとすることは公正とはいえないから,そのような行為を不正競争行為として禁ずることにしたものと解される。このことからすれば,不競法19条1項5号イの『最初に販売された日』に係る『商品』とは,保護を求める商品の形態を具備した最初の商品を意味するのであって,このような商品の形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品を意味するものではないと解すべきである。原告は,原告テントの第2世代を第1世代と比較すると,①高さ調節を変更した点,②シルバーコーティングによるUVカット加工を施した点,③支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更した点,④収納バッグの色を変更した点,⑤耐水圧及びシームシーリングを施した点で異なるから,上記『商品』とは第2世代の原告テントを指し,その販売開始日である平成25年10月15日を『最初に販売された日』とすべき旨主張する。しかし,本件全証拠を精査しても,そもそも原告テントに第1世代と第2世代があり,第2世代は第1世代と上記①ないし⑤の全ての点で異なっていることを示すに足りる的確な証拠は見当たらない。・・・(中略)・・・仮に原告の主張するとおり,原告テントに第1世代と第2世代があり,第2世代は第1世代と上記①ないし⑤の全て点で異なっているとしても,・・・(中略)・・・原告が保護を求める商品の形態は第1世代から具備されていたものというべきである。・・・(中略)・・・以上からすれば,原告の主張する原告テントの第2世代における変更点は,そもそも不競法2条1項3号の『商品の形態』を変更するものではないか,仮に『商品の形態』を変更するものであるとしても,原告テントの第1世代の商品形態を具備しつつ若干の変更を加えたものにすぎないというべきであるから,第1世代と第2世代は実質的に同一の形態であるものといわざるを得ない。以上によれば,原告の主張を前提としても,原告が保護を求める商品の形態を具備した最初の商品は,第2世代の原告テントではなく,第1世代の原告テントであるというべきである。そして,第1世代の原告テントが日本国内で最初に販売されたのは平成22年10月頃というのであるから(前記第2,2(2)),被告テントの販売開始時点である平成27年5月2日時点では,既に3年が経過していることになる。したがって,被告による被告テントの販売には,不競法19条1項5号イの適用除外事由があり,そもそも同法3条及び4条の適用がない。」
原告(カエルム株式会社)は、「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(以下、「本願商標」とする)について、平成25年9月30日にした登録出願(商願2013-76166号)の分割出願として、平成26年6月9日に第9類,第18類,第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願(商願2014-47082以下、「本願」とする)をしましたが,平成27年3月26日付けで拒絶査定を受けたので、同年6月26日付で、拒絶査定不服審判請求をしました(不服2015-12178号)。
原告は、その後2回手続補正を行いその結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となりました(本願役務)。
特許庁は、この不服審判に対して、平成28年6月24日「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしましたが、原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を起こしました。
審決理由の要点は、本願商標「NYLON」は、「(合成繊維の)ナイロン」を表す語として一般に知られているので、本願商標を、その指定役務である被服、履物及びかばん類を取扱商品とする小売等役務に使用するときは、これに接する需要者は、「当該小売等役務で取り扱われる商品がナイロン製の商品であること」と受け取るであろうことから、自他役務識別機能を果しえないと考えられるので商標法3条1項6号に該当するというものです。
原告であるカエルム株式会社は、「NYLON/JAPAN」というファッション誌を発行している会社です。
原告は、本願商標は、各構成文字及び全体の構成態様に特徴があるから「NYLON」の欧文字を「普通に用いられる方法で」横書きしてなるものではないこと、大文字「NYLON」が単独で商品の原材料として商品に表示される状況にはないこと、アンケート調査を実施したところ「NYLON」を「ナイロン」と読めた人は回答者の約29%しかおらず、本願商標から直ちに合成繊維「ナイロン」を想起する者の数は少ないので品質等表示にあたらないこと、原告が出版している雑誌「NYLON/JAPAN」との関係に基づいて識別標識としての機能を発揮していることなどを理由に商標法3条1項6号には該当しないと主張しました。
知財高裁は、本願商標は、「Futura」と称する書体を太字で表したものと酷似しており、欧文字の大文字「NYLON」を一般に知られている書体によりありふれた大きさと配置で横書きしたにとどまるものであるから,欧文字の大文字「NYLON」普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認識されるにとどまるものと認められ、本願役務は、「被服,履物,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり、取扱商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に取扱商品の販売により収益を上げるためのサービス活動をいい、顧客の商品選択が容易となるように、商品の原材料(素材)その他の特長等を説明することも含まれるから、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該指定役務の小売の業務における取扱商品である被服、履物、かばん類及び袋物の原材料(素材)として相当程度利用されているナイロンを表したものと認識するにとどまり、役務の出所を表示するものと認識するとはいえないから、本願商標は、自他役務の識別力を欠くものと認められるので商標
法3条1項6号に該当するとした審決の判断に誤りはないとしました。
原告は、日本を代表するメガバンクの一つで、三井住友グループの中核的企業である株式会社三井住友銀行です。
被告は、三井住友グループの承認を受けていないにもかかわらず、自らを「三井住友グループ」の一員であるとしてウェブページ等に掲載しているので、原告は被告の行為は、不正競争防止法2条1項1号、2条1項2号に該当するとして「三井住友」にかかる表示の使用の差止を請求しました。
大阪地裁は、「被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば、『三井住友』との営業表示が原告及びその企業グループを示すものとして著名であること、被告が、別紙『表示目録』記載のとおり、自己の営業表示として『三井住友』との営業表示と同一のものを使用していることが認められるから、被告の行為は、不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当する。 そうすると、被告の行為によって原告の営業上の利益が侵害されていると認められるから、原告の被告に対する同法3条1項、2項に基づく請求は理由がある。」として、被告に対し、「三井住友」の文字を含む企業集団に属する旨の表示及び三井住友グループメンバー企業として認可されている旨の表示をしてはならないとの判決を下しました。
原告は、コーヒー関連事業等を行うUCCグループを構成する各会社の株式等を保有して当該会社の事業活動の支配、管理業務等を目的とする株式会社で、第39類「車両による輸送等」について「UCC」のロゴマーク商標を有しています。
一方、被告の株式会社ユー・シー・シーは、一般貨物自動車運送事業等を目的とし、主にバイクによる荷物の輸送・配送を業務とする株式会社です。
被告は、平成27年1月30日に「株式会社ユー・シー・シー」(以下、「被告商号」という。)なる商号で、一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業等を目的として設立され、その旨の設立登記が大阪法務局同日付けでなされていて、そして、被告商号をインターネット上のウェブサイト(URL:http://www.ucc-bike.com/)その他において、バイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)を業務とする自己の商号として使用しています。
原告は、被告の行為は不正競争防止法2条1項2号に該当するとして、被告標章の差止請求及び被告商号登記の抹消登記手続を求めて本件訴訟を提起しました。
大阪地裁は、「被告は、適式な呼び出しを受けながら、口頭弁論期日に出頭せず、何ら準備 書面を提出しないから、請求原因...の各事実を自白したものとみなす。...被告商号『株式会社ユー・シー・シー』は、会社の種類を区別する『株式会社』を除いた『ユー・シー・シー』部分が識別力を有する要部となるが、当該 要部『ユー・シー・シー』と、原告のUCC商号は、いずれも称呼が『ユーシーシー』であり、同一である。また、いずれも、特別な観念は生じない。したがって、被告商号『株式会社ユー・シー・シー』と原告のUCC商号とは、類似している。...被告標章は、いずれも本件商標と称呼が同一であり、特別な観念が生じない点も共通する。したがって、被告標章1ないし3は、いずれも本件商標と類似している。また、被告役務であるバイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)は、本件商標の第39類の指定役務「車両による輸送等」に該当し、又は、類似しているから、被告の役務は、本件商標の指定役務と同一又は類似である。以上によれば、原告の被告に対する請求はすべて理由がある。」として、被告各標章の使用の差止及び商号の抹消登記手続の請求が認容されました。
原告は、「くしゃっと水切りざる」という商品名でシリコン素材のざるを販売しています。一方、被告らは「なんでもござる」という商品名でシリコン素材のザルを販売しています。
原告は、被告の行為は不正競争防止法の2条1項1号又は2条1項3号に該当するとして本件訴訟を起こしました。大阪地裁は、2条1項1号と2条1項3号該当性について以下のように判断しました。
【1】2条1項1号に該当するか
大阪地裁は、「原告商品は、ざるとしての機能に加え、柔軟性があり、変形させることができるという機能もあり、これにより従来のざるにはない用途に用いることができるというものである。そうすると、柔軟性があり、変形させることができるという形態的特徴は、原告商品の機能そのもの又は機能を達成するための構成に由来する形態であり、...商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態として、法2条1項1号の商品等表示には当たらないというべきである。具体的にみると、基本的形態として原告が主張する構成は、いずれも、柔軟性を持たせるための構成若しくは柔軟性があるという機能それ自体又はざるとしての機能を発揮させるための構成であり、商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態であるというほかない。また、使用時形態も、柔軟性があり、変形させることができるという機能の結果生じる形態であり、これも商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態、結果である。」として2条1項1号には該当しないとの判断を示しました。
【2】2条1項3号に該当するか
大阪地裁は、「法2条4項によれば、『商品の形態』とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。...原告商品の使用時形態それ自体が、法2条4項により保護される商品の形態(形状)であるかはおいても、使用時形態のように変形自在であるという原告商品の特性は、少なくとも需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる質感等に反映されることは明らかであり、法2条1項3号により保護されるべき商品の形態として十分に考慮されるべきものである。被告らが主張する上記各書証に記載されたざる等のうち、乙2に記載されたシラスティック製水切りボールはシリコンゴム材料を素材とするものであるが、取っ手部分があり、ざるの部分にもリムがないなど、原告商品の形態と大きく異なるものである。乙3に記載された合成樹脂製ざるについても、二個のざる体をセットにしたものであり、原告商品のように変形自在にしたものでもなく、質感についても大きく異なる。...他に、原告商品と同様に変形自在であって、しかも原告商品と同一の形態の先行商品が存在することを認めるに足りる証拠はない。...被告らは、原告商品の形態は、シリコン素材を使用したという技術的構成から必然的に由来するものであり、商品の機能を発揮するために不可欠な形態であるとも主張する。しかしながら、ざるの素材を変形自在なものにしたとしても、ざるとしての基本的形態だけを取っても、材質の選択、肉厚幅、底面突起の数、底面突起の有無及び数、表面上の穴の大きさ及び数など、その形態選択には無数の選択肢があることからすれば、原告商品の形態を全体として評価したときに、それが商品の機能を発揮するために不可欠な形態のものであるということはできない。」として2条1項3号に該当するとの判断を示しました。
控訴人は、医薬品等の製造販売等を業とする株式会社です。被控訴人は、ドラッグストア等の店舗において、医薬品、化粧品等の販売を行うこと等を業とする株式会社です。被控訴人は、奈良県、広島県等に所在するドラッグストアにおいて、販売チラシに控訴人商品についてその仕入価格と「定価」を併記して比較した販売チラシを用い、「原価セール」と題して、仕入価格で控訴人商品を消費者に販売していました(以下、上記の行為を「原価セール」という)。控訴人は、仕入価格は営業秘密であり、被控訴人が仕入価格を開示した「原価セール」は不正競争防止法2条1項7号に該当するとして、損害賠償請求等を行いました。
東京高裁は、「不正競争防止法2条1項7号は、『営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為』を『不正競争』であるとするものである。すなわち、同規定は、営業秘密を保有者から『示された』者が、不正競業などの目的をもって、その営業秘密を不正に開示するなどの行為を対象とするものである。そこで、検討するに、被控訴人は、控訴人商品に関する被控訴人ダイコクと控訴人との間における売買代金額(仕入価格)という情報を『示された』ものではないのであるから、これを一般消費者に開示しても、不正競争防止法2条1項7号が対象とする行為には該当しないことが明らかである。」として価格の開示行為は、不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為には該当しないと判断しました。
本件の控訴人(原告)は、プロパンガス(以下「LPガス」という。)、石炭、木炭、薪その他一般燃料及び燃料器具の販売等を営む株式会社です。被控訴人(被告)は、液化石油ガス、石油製品の製造及び販売、石油製品の配送業等を営む株式会社である。控訴人は、被控訴人からLPガスを仕入れており、控訴人の顧客名簿を交付した上でLPガスの配送についても委託していました。その後、控訴人と被控訴人の契約は終了しました。被控訴人は、控訴人との契約終了後に、控訴人との契約に基づいてLPガスを供給していた控訴人の顧客に対し、被控訴人との間でLPガス供給契約を締結することを求める営業活動(以下「本件営業活動」という。)を行い、控訴人の顧客約680軒を被控訴人の顧客として獲得した。控訴人は、被控訴人の行為は、不正競争防止法2条1項7号に該当するとして、本件訴訟を起こしました。
知財高裁は、「本件契約において、『一般消費者等の秘密を他に洩らしてはならない。』旨の守秘義務条項が定められていたとしても、控訴人の顧客名簿について、控訴人及び被控訴人のいずれにおいても、営業秘密である旨が明示され、閲覧することができる者が制限されるなどの厳格な管理がされておらず、また、控訴人から被控訴人に対して、秘密として管理するように具体的に指示されたものではない以上、控訴人の顧客名簿について秘密管理性が認められないことは明らかである。したがって、控訴人の顧客名簿は、不正競争防止法における営業秘密に該当するものではないから、被控訴人が控訴人の顧客に対して行った本件営業活動に際して控訴人の顧客名簿が使用されたことがあったとしても、同法2条1項7号の営業秘密の不正使用に該当するものということはできない。」と判断しました。
原告は、魔法瓶、保温容器及びその部分品類の製造販売並びに輸出入等を業とする株式会社です。被告は、各種金属類加工修理製作販売等を業とする株式会社です。
被告は、平成20年1月頃から、ステンレス製真空マグボトルを輸入し、日本国内で販売しています。原告は、被告の行為が不正競争防止法2条1項3号の「不正競争」に当たるとして、差止及び損害賠償請求等を行いました。
大阪地裁は、「被告物件は...浙江剛自達不銹鋼制品有限公司により、遅くとも平成15年8月には中国国内において製造販売されていたものと同一のものと認められる。...他方で、原告は平成19年9月から原告物件を販売したものであり、原告従業員の陳述書によっても、原告物件のデザイン作成を開始したのは平成18年11月というのであるから、被告物件と同一である中国商品は、原告物件が日本国内において販売されるより先に中国において製造販売されていたものと認められる。...被告物件は原告物件より先に中国国内において製造販売されていたものと認められるから、被告物件が原告物件の形態に依拠して作り出されたものでないことは明らかであり、よって、被告物件が原告物件の形態を模倣した商品に該当しないこともまた明らかというべきである。」として原告の請求を棄却しました。
本件の被上告人X1は米国法人でアメリカンフットボールのプロチームの名称及びシンボルマーク(以下、「本件表示」とします。)の商業的利用について管理しています。被上告人X2はX1から本件表示及びその商品化事業を許諾されたも日本法人です。
上告人Yは、本件表示が印刷されたシートで被覆したロッカーを販売していました。そこで、X1とX2は上告人に対して差止請求及び損害賠償請求などを行いました。
最高裁は、「ある営業表示が(旧法)不正競争防止法1条1項2号所定の他人の営業表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両表示を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準として判断すべきものであることは当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和五七年(オ)第六五八号同五八年一〇月七日第二小法廷判決・民集三七巻八号登載予定)、また、ある商品表示が同項一号所定の他人の商品表示と類似のものにあたるか否かの判断についても、前示営業表示の類似判断の場合と同一の基準によるべきものと解するのが相当である。...不正競争防止法1条1項1号又は二号所定の他人には、特定の表示に関する商品化契約によつて結束した同表示の使用許諾者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解するのが相当であり、また、右各号所定の混同を生ぜしめる行為には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず、自己と右他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し、混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である。」との判断を示しました。